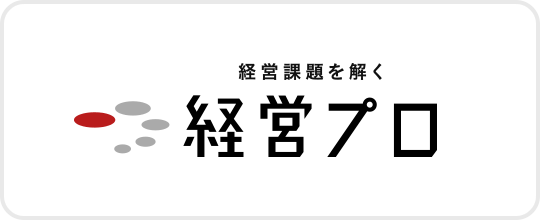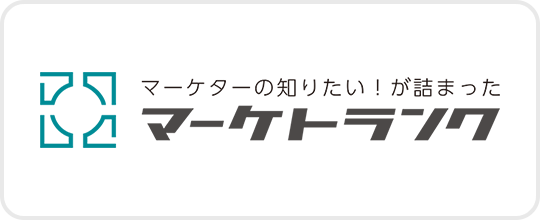傾聴とは、相手の話を単に聞くだけでなく、相手の言葉に耳を傾け、心を込めて聴く技術のことです。相手の話を否定せずに受け入れ、共感的な態度で接することで、相手との信頼関係を構築する上で非常に効果的な方法として注目されています。
特に、リモートワーク環境下では、非言語コミュニケーションが制限されるため、より意識的に傾聴のスキルを活用する必要があります。
マネジメントの観点からも、傾聴は欠かせません。コミュニケーション能力の向上を目指す上で、傾聴は避けては通れない重要なスキルであり、個人のキャリア発展やチームの成功に大きく寄与する要素となっています。
今回は「傾聴」が注目される社会背景とともに、傾聴の重要性や傾聴力を上げるための方法を解説します。
なぜ今、傾聴なのか
コロナ禍がビジネスの場にもたらした影響はさまざまですが、中でも大きなものとして、リモートワークをはじめとしたコミュニケーション方法の変化があげられるでしょう。今まで直接顔を合わせて行うことができたコミュニケーションの非対面化が進み、その難しさを実感している人も増えています。
関連記事:テレワークで効果的なコミュニケーションは「雑談」!鉄板の雑談ネタ10選
このような状況下で、傾聴の重要性が高まっています。ZaPASSJAPAN株式会社が行った「チームマネジメントに関するアンケート」の結果によると、「テレワークになったことで、チームマネジメントの難易度に変化がありましたか?」という設問に対して、「とても難しくなった」と「やや難しくなった」の回答が合わせて67.6%と、7割近くの人がリモートワークによって、チームマネジメントが難しくなったと感じていることがわかりました。
さらに、同調査の「テレワークになったことで、チームマネジメントにおいて傾聴力がより必要になったと思いますか?」という設問に対しても、「はい」の回答が86.2%となっており、9割近くの人がリモートワーク下における傾聴の必要性を感じているという結果になりました。
参考:ZaPASS JAPAN 株式会社「チームマネジメントに関するアンケート」
傾聴とは、相手のいうことに対して否定をせず、相手の話に耳も心も傾けて「聴く」会話のテクニックのことを指します。もともとはカウンセリングにおける技法で、心理学などの分野では以前からよく使われている言葉でした。「ただ熱心に話を聞くだけなのでは?」と思うかもしれませんが、意識すべきなのは、相手に共感し、信頼していると示すことで、傾聴ができるようになると、信頼が生まれ、社内の人間関係が良好になるといわれています。
また、経済産業省が提言している「社会人基礎力」の要素にも「チームで働く力(Teamwork)」の一つとして「傾聴力」は含まれています。このことからも、傾聴がビジネスにおいて重要なスキルとして認識されていることがわかるでしょう。
傾聴の実践には、相手の話を真摯に受け止め、共感的な態度で接することが求められます。これは、リモートワーク環境下でのコミュニケーションにおいて特に重要です。画面越しのやり取りでは、非言語コミュニケーションが制限されるため、相手の感情や真意を汲み取ることが難しくなります。そのため、より意識的に傾聴の姿勢を示し、相手の言葉に耳を傾ける必要があるのです。
さらに、傾聴は単に相手の話を聞くだけでなく、適切な質問や確認を行うことで、相手の考えをより深く理解することにもつながります。これは、リモートワーク下での情報共有や意思疎通の質を高めるうえで非常に有効な手段です。
以上のように、現在のビジネス環境において傾聴の重要性が高まっている背景には、コミュニケーション方法の変化や、それに伴うマネジメントの難しさがあります。傾聴を意識的に実践することで、これらの課題に対応し、より効果的なチームワークや生産性の向上につなげることができるでしょう。
ロジャーズの3原則と傾聴のメリット
傾聴は、アメリカの心理学者でカウンセリングの祖といわれるカール・ロジャーズによって提唱された重要なコミュニケーション技術です。ロジャーズは傾聴を「積極的傾聴(active listening)」と呼び、自らが行った多くのカウンセリングの事例を分析して、話を聴く側には3つの要素が必要であると説いています。これらの要素は、ビジネスシーンでも効果的な傾聴を実践する上で重要な指針となります。
ロジャーズの3原則
- 自己一致(congruence)
これは、相手と自分が見ているものを一致させることです。相手への理解が十分でないと、話を進めた先で見解の違いが生じてしまうため、話を聴いて理解ができないことやわかりにくいことをそのままにせず聴き直すなど、常に相手の真意を確認することが必要です。そうすることで、やりとりの過程で相手の感じ方や考え方を正確に把握できるようになります。傾聴の実践において、自己一致は相互理解の基盤となる重要な要素です。 - 共感的理解(empathic understanding)
相手の話を、相手の立場で、相手の気持ちに共感しながら聴いて、理解しようとすることです。相手の言葉を受け入れるためには、まず相手の言葉を引き出すことが必要となるため、「思ったことを素直に言ってもいい」という雰囲気を作り出さなければなりません。そのため「共感」は、相手に心理的な安心感を与えるためにも重要なポイントとなるのです。傾聴における共感的理解は、相手の内面に寄り添い、深い理解を促進します。 - 無条件の肯定的配慮(unconditional positive regard)
相手の話に対して、善悪や好き嫌いの評価をせずに、一旦すべて承認するということです。言葉を引き出すためには安心感が必要であると述べましたが、口から出した言葉を承認することでためらいを和らげることができます。重要なのは、相手の話を否定せず、なぜそのような考えに至ったのか、その背景に対して肯定的な関心を持って聴くことです。そうすることで、相手は安心して話をすることができ、核心に迫る言葉を引き出すことが可能となります。傾聴において、無条件の肯定的配慮は相手の本音を引き出す鍵となります。
では、傾聴にはどのようなメリットがあるのでしょうか。順番に紹介していきましょう。
傾聴がもたらすメリット
- 信頼関係の構築がしやすくなる
傾聴を意識しないコミュニケーションでは、相手の話を軽く流してしまったり、興味関心があることだけを熱心に聞いたりするといったことも珍しくありません。しかし、そのような態度で相手の心を開くことはできないでしょう。傾聴を意識して、相手の話を真剣に聴き、共感や理解しようとすることで、相手も肯定的な感覚を得ることができ、心を開くこと、すなわち信頼関係の構築につながっていきます。ビジネスにおいて、傾聴は良好な人間関係を築く上で欠かせないスキルです。 - 心情や問題の整理ができる
傾聴してくれる聴き手がいることで、話し手は自らの心情や意見、現在抱えている問題などを整理することができます。人はさまざまな悩みや意見を持っていますが、具体的な言葉にして表現できるレベルの考えもあれば、まだ他人に伝える程度にはまとまっていない考えや、自らも気づいていないような考えもあるでしょう。それを言葉にして把握するのは簡単なことではありませんが、傾聴することで、話し手は自分の考えを何とか伝えようと言語化し、それを口に出すことで自分の本心や意見に気付くことができます。これを繰り返し行うことで考えや感情、問題などの整理ができ、具体的な行動へとつながるのです。傾聴は、問題解決のプロセスを促進する重要な要素となります。 - 仕事が円滑に進む
傾聴は仕事の効率にも良い影響を与えます。ビジネスでは、互いへの理解不足や信頼関係が築かれていないことなどが原因となって、仕事が円滑に進まないといった事態が生じることもあるでしょう。傾聴によって、相手の意見や考えに真摯に耳を傾け、時に効果的な質問を挟むことで、話し手の伝えたいことを引き出すことができ、コミュニケーションが深いものとなります。スムーズなコミュニケーションを行えることは、結果として仕事が効率的に進むことにもつながるのです。傾聴は、ビジネスにおける生産性向上にも寄与する重要なスキルと言えます。
傾聴の実践は、ビジネスシーンにおいて多くのメリットをもたらします。相手の話に耳を傾け、理解しようとする姿勢は、良好な人間関係の構築や効果的な問題解決、さらには業務効率の向上にもつながります。ロジャーズの3原則を意識しながら傾聴のスキルを磨くことで、コミュニケーションの質を高め、より円滑なビジネス展開が可能となるでしょう。
傾聴を行う際の注意点とトレーニング方法
さまざまなメリットが享受できる傾聴ですが、傾聴には技術が必要です。傾聴スキルを向上させるためには、適切なトレーニングと実践が欠かせません。準備をせずに行うと、心理的なストレスがたまる要因にもなるからです。そこで、傾聴をトレーニングする際の注意点と傾聴のトレーニング方法を見ていきましょう。
傾聴をトレーニングする際の注意点
- 聴いた内容は基本的には他言しないこと
- 聴いた話に関する自分の責任がどこまでなのかを見極めること
聴いた話を気軽に他人に話してしまったことで、相手が「あなただから話したことなのに、どうして他人に言ってしまったのか」と思ったとしたら、信頼関係を築くことは困難になります。しかし、「会社のお金を横領した」などと打ち明けられた場合には、決して自分の中に留めておくというわけにはいきません。
傾聴する際には、「他言はしない」というルールをよく理解したうえで、自分がどの程度の話なら責任を負うことができるかや、自分では扱いきれない話を聴いたときにどうするのかは明らかにしておく必要があります。
傾聴のトレーニング方法
次は傾聴のトレーニング方法について見ていきましょう。傾聴スキルを磨くことで、ビジネスコミュニケーションの質を向上させることができます。
- 話しやすい環境を自分自身で考えてみる
話しやすい雰囲気や環境とはどのようなものなのか、また、どういった身振りや手ぶり、表情をすれば話しやすい雰囲気を生み出すことができるのかなど、自分自身を点検してみると良いでしょう。傾聴の基本は、相手が安心して話せる環境を作ることから始まります。 - 4つの技術を使って話を聴く
相手の話を聴くうえで、「うなずき」「あいづち」「繰り返し」「言い換え」という4つの技術を使い分けると、話に共感していることが伝わるため、話しやすい空気をつくることができます。
たとえば、「繰り返し」は、「あなたは〇〇と思っているのですね」と相手の言葉を繰り返すことで、話をしっかり聴いているという印象を与え、さらなる会話を引き出すことができるでしょう。
傾聴を行うと、相手に共感をしようという意識が強くなり、会話が行き詰ってしまうこともあり得ますが、そんなときにはこれらの技術を使うことで、相手からさらに話を引き出すことや、話題を膨らませることができるでしょう。 - 5W1Hを意識する
相手の話をよく理解するには、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのようにした」の5W1Hを意識することがポイントです。
会話に行き詰ってしまった場合や、話をよく理解できなかった場合には、5W1Hのうち、どれかを聴き逃していないかを考え、確認すると良いでしょう。 - アクティブリスニングを実践する
アクティブリスニングとは、相手の話を積極的に聴く姿勢のことを指す。単に相手の話を聞くだけでなく、相手の感情や考えを理解しようと努める態度が重要です。これにより、相手との信頼関係を深めることができます。 - 非言語コミュニケーションにも注目する
傾聴では、言葉だけでなく、相手の表情やジェスチャー、声のトーンなどの非言語的な要素にも注意を払うことが大切です。これらの情報から、相手の本当の気持ちや意図を読み取ることができます。 - 傾聴の練習パートナーを見つける
友人や同僚などと傾聴の練習をすることで、実践的なスキルを身につけることができます。お互いにフィードバックを行い、改善点を見つけ合うことで、効果的に傾聴力を向上させることができるでしょう。 - 傾聴の記録をつける
傾聴の実践後、その内容や気づきを記録することで、自身の傾聴スキルの成長を確認できます。また、記録をつけることで、傾聴の重要性を再認識し、モチベーションの維持にもつながります。 - 定期的に傾聴スキルを振り返る
傾聴スキルの向上は継続的な努力が必要です。定期的に自身の傾聴スキルを振り返り、改善点を見つけることで、より効果的な傾聴ができるようになるでしょう。
これらのトレーニング方法を実践することで、傾聴スキルを着実に向上させることができます。傾聴は、ビジネスにおいて重要なコミュニケーションスキルの一つであり、信頼関係の構築や問題解決に大きく貢献します。日々の業務の中で意識的に傾聴を心がけ、継続的にスキルアップを図ることが、ビジネスパーソンとしての成長につながるでしょう。
まとめ
リモートワークが浸透し、非対面でのコミュニケーションが増えた現代において、傾聴はこれまで以上に重要なビジネススキルとして注目されるようになりました。単に相手の話を聞くだけでなく、相手の言葉に耳を傾け、心を込めて聴く技術である傾聴は、相手を否定せず受け入れ、共感的な態度で接することで、強固な信頼関係を築く上で不可欠です。
ある調査では、リモートワークでチームマネジメントが難しくなったと感じる人が多く、そのほとんどが傾聴力の必要性を感じていることが示されています。また、社会人が持つべき基礎力の一つとしても傾聴力は挙げられており、ビジネスにおけるコミュニケーション能力向上、ひいては個人のキャリア発展やチームの成功に大きく寄与すると認識されています。
傾聴の基礎となるのは、アメリカの心理学者カール・ロジャーズが提唱した「自己一致」「共感的理解」「無条件の肯定的配慮」の3原則です。これらを実践することで、信頼関係の構築、話し手の心情や問題の整理、そして仕事の円滑化といったメリットが期待できます。
傾聴スキルを向上させるには、適切なトレーニングと実践が欠かせません。トレーニングでは、聴いた内容の他言をしないことや、自身の責任範囲を明確にするといった注意点を守ることが重要です。具体的なトレーニング方法としては、話しやすい環境の自己考察、「うなずき」「あいづち」「繰り返し」「言い換え」といった4つの技術の活用、5W1Hの意識、アクティブリスニングの実践、非言語コミュニケーションへの注目などが挙げられます。また、練習パートナーとの実践や記録、定期的な振り返りも効果的です。
これらの方法を日々の業務で意識的に実践し、継続的にスキルアップを図ることで、リモートワーク時代におけるビジネスコミュニケーションの質を高め、より効果的なチームワークと生産性の向上を実現できるでしょう。