社内での従業員間でのURL伝達や、顧客やクライアントに対してのブランド認知、ターゲティング、キャンペーンでの活用など、様々な場面で短縮URLを利用している方も多いのではないでしょうか。そんな中、「goo.gl」でおなじみのGoogle公式の短縮URLサービスは2025年8月に完全終了を迎えます。当該サービスで既に生成済みのURLを、気にせずずっと運用していたという方は注意が必要です。
本記事では、そもそも短縮URLとはどういったものなのか、活用シーン、「goo.gl」終了の詳細や代替となる著名な短縮ツールなどを紹介しています。
目次
短縮URLとは

まずは、短縮URLについての基本的な知識を簡単にご紹介します。
短縮URLは長いURLを短いURLへ変換したもの
短縮URLサービスを利用して既存のURLを変換すると、そのサービスの仕様にもよりますが、だいたい10文字ちょっと程度のとても短いURLへ変えることができます。
具体的には、変換後は以下のような状況となります。
・元々のURL →引き続き存在しているため、このURLも使える状態
・短縮URLサービスで生成した短いURL →こちらでアクセスしても、上記と同じ場所(ページ)へ転送される
日常生活の中でも、とても長い、人間の目で見てほぼ意味のとれないような文字列(機械的な属性指定など)を含むURLを目にしたことがあるかと思います。例えば地図サイトで、細かな条件指定をおこなった先での特定の地点が表示されたページのURLや、ECサイトでの商品検索結果の一覧ページのURL、キャンペーンや広告ページを通過したうえでたどり着いた普段とは違う長さの公式サイトURL、といった類です。
このようなURLを、グッと短いURLへ変換したものが、短縮URLです。
ちなみに、短縮URLサービス自体は長いURLでなければ使えないということはなく、基本的にどのようなURLであっても、サービスごとの一定のルールに基づいて変換されます。
短縮URLを使うメリット
短縮URLには多くのメリットがあり、自社内での運用であっても、顧客へ特定のとても長いURLを短く分かりやすく伝えるときであっても重宝します。
電子メールやチャットツール、SNS、クラウドのドキュメントなどでURLを伝達する場合を想定すると、「長くても、手書きするわけじゃないので短縮する必要がないのでは?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。特に、連絡ツール側で長いURLの表示が自動的に一部カットされるような仕組みがある場合には、それで充分と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、見映えの悪い機械的な文字列を一部だけでも目にさせてしまうよりは、一定のルールできれいに短縮されたURLを見せる方が、相手側が持つ印象も異なります。また、長いURLがそのまま表示されてしまうツールの場合には、見た目上でごちゃごちゃしてしまうだけでなく、レイアウト崩れや、スクロール量の増加、情報視認性の低下、大切な情報を読み落とされてしまうなど多くのリスクがあります。短縮URLでこのような問題を回避できるのです。
さらに、紙の資料やオフラインの掲示物など、掲載スペースが限られている箇所へURLを記載しなければならない場面でも、当然のことながら短いURLのほうが適しています。
様々な短縮URLサービスの中には、URL変換と合わせて、そのURLに紐づいたQRコードを発行できるものもあります。QRコードであれば尚更、オフラインの掲示物の読み取りしやすい位置に載せておいたり、配布資料に印刷しておいたりと活用方法が広がり、手間のないアクセス手段の提供にもつながります。
▼こちらの記事でも、短縮URLサービスの特徴や様々な活用シーンをご紹介しています。ぜひ合わせてご覧ください。
短縮URLとは?メリット・デメリットと無料サービス11選
短縮URLを使うデメリット
短縮URLは基本的に大変便利なサービスですが、ビジネスで運用する際には念頭に置いておきたいデメリットもあります。
短縮URLでは元々のURLに含まれていたドメインや、その他のURL要素(カテゴリやサイト内の階層構造を伝える文字列など)が隠れてしまうため、そういったことまで含めて伝えたい場合には不適切となります。
対外的に使う場合にもせっかくの自社ドメインを伝えられない、アクセスすることについてむやみな警戒を招いてしまう……といった点が考えられますので、使う場面や伝え方を検討したうえで活用するようにしましょう。
また、短縮URLサービスを使うということは、すなわち自社サイトと、そこへアクセスする顧客との間に他社の変換サービス(および、その変換を実現するサーバーなど)が介入するということにもなります。
そのため、セキュリティや情報の取り扱い、サービスの安定性や信頼性などの面から、著名なサービス・利用者の多いサービスなどを慎重に選ぶようにしておきましょう。
関連記事
・短縮URLとは?メリット・デメリットと無料サービス11選
・URL(ユーアールエル)とは?初心者でも分かるように解説
長いURLをもとに短縮URLが生成される仕組み

短縮URLサービスが提供しているURL短縮の仕組みは、簡単にまとめると以下のような流れで実現しています。
1、ユーザーがURL短縮のWebサービスやアプリケーション上で、元のURL(長いURL)を入力し、処理のリクエストを送信する
2、サービス側のサーバーが長いURLを受け取り、データベースに登録したうえで対となる短縮URLを生成する
3、URL短縮のWebサービスやアプリケーション上で、短縮URLが表示される
4、ユーザーや第三者などから短縮URLへのアクセスが行われた場合、サービス側のサーバーがリダイレクト処理を行い、元の長いURLが示す正しい場所へ転送させる
以下では、この「リダイレクト」についてもう少し詳しく解説します。あわせて、既存のURL短縮サービスを使わずともこのリダイレクトを実現する方法として、「.htaccess」についてもご紹介します。
リダイレクトとは
「リダイレクト」は、特定のページへアクセスしたユーザーを、紐づけられた別のページへ自動的に転送するための仕組みです。
例えば、自社のWebサイトのリニューアルが行われ、ユーザーが過去に知っていた(ブックマークしていた)個別のURLが無効になってしまっている状況の場合に、サイト側で該当する新しいページへのリダイレクトを設定しておけば、ユーザーを自動的に新しいページへ誘導することができます。
このリダイレクトには、大きく分けてWebサーバー側が実行するように設定された「サーバーサイドリダイレクト」と、ユーザーが使用しているブラウザ側で実行するように設定された「クライアントサイドリダイレクト」があります。
.htaccess(ドットエイチティーアクセス)とは
「.htaccess」は、前述のサーバーサイドリダイレクトを実現する際、Webサーバーを制御するために使われる設定ファイルのことです。この.htaccessは、Webサーバーが「Apache(アパッチ)」と呼ばれるWebサーバーソフトで構築されている場合に有効です。
この.htaccessの仕様を理解し、例えば自社サーバー(Apacheで構築)内で適切な.htaccessファイルを設置しておけば、自前で「短いURLから長いURLへの自動転送」を実現することも可能です。
この方法であれば、自社ドメインを含んだ公式感のある短縮URLを顧客に見せることもできます。
▼以下の記事では、URLのリダイレクトや.htaccessファイルの記述についてさらに詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
リダイレクトとは?種類や設定方法、htaccessファイルの書き方
httpとhttpsの違いとは?リダイレクトやセキュリティも解説
Google公式の短縮URLサービス「Google URL Shortener(goo.gl)」は、2025年夏に既存URLのリダイレクトを含め完全終了!
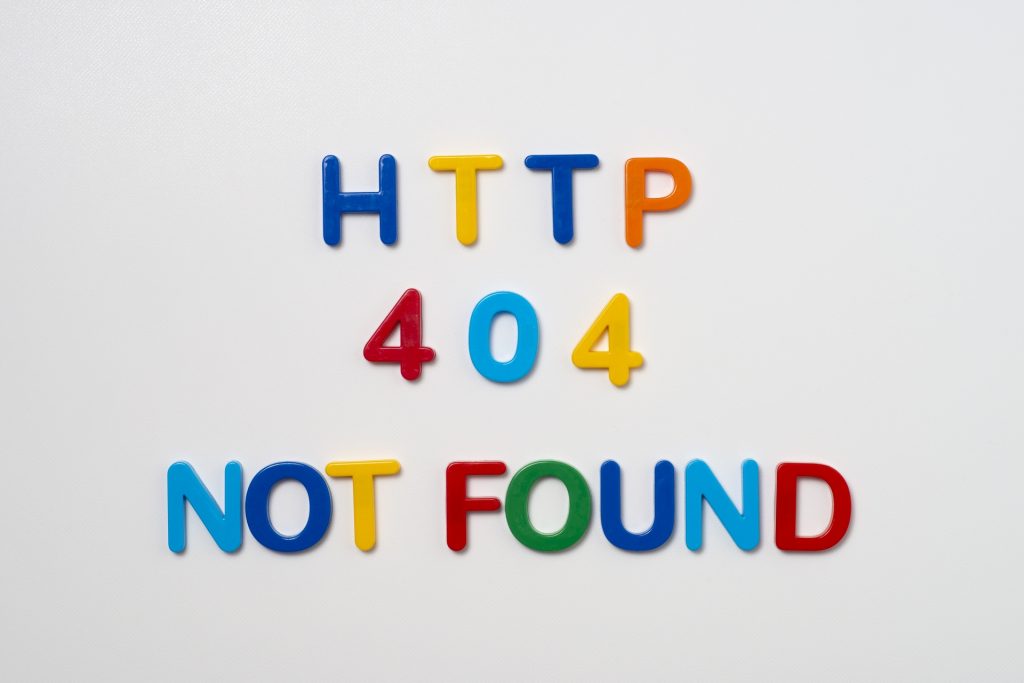
Google社が公式に提供している短縮URLサービス「Google URL Shortener(goo.gl)」は利用者が大変多い著名なサービスであるため、過去に活用していたという方や、当該サービスで生成された「https://goo.gl/~~」といった短いURLを今も活用しているという方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、このサービスは【2025年8月25日】に完全終了することが決定しているため、注意が必要です。
実は、短縮URLの新規作成自体はすでに停止していたのですが、生成後の短縮URL自体や、リダイレクトは動作していたという状況が長らく続いていました。上記の完全終了を迎えると、これらの動作もすべて、完全に停止します。
もしサービス終了後に当該URL(goo.gl)を使い続け、例えば自社の顧客にそのURLを伝えたとしても、顧客は応答を返さないURLへアクセスしてしまうこととなります。そのため、別のURL短縮方法へ運用を切り替えておく、関係各所に早めに更新されたURLを周知共有しておく、といった対応が必要です。
※Google公式の短縮URLであっても、GoogleフォームやGoogleマップといった、Google関連アプリ・サービスの一貫として生成される一部の短縮URLは引き続き有効です。詳しくは、下記の公式アナウンス情報をご確認ください。
Google URL Shortener リンクが利用できなくなります(Google for Developers)
Googleサービス終了後の代替を探している方へおすすめのURL短縮ツール

最後に、様々なベンダーから提供されているURL短縮ツール・サービスをご紹介します。
「goo.gl」の提供終了以降の代替サービスを検討されている方は、各公式サイトの情報や利用規約などもご覧のうえ、自社に合ったサービスを選定してください。
各サービスを移行先として比較する際には、付加機能、セキュリティ、サポート体制やサービス自体の信頼性・ブランド力、無料で使える機能の範囲など、目的に応じた視点で検討することをおすすめします。
Bitly
サービスページ上の入力フォームから簡単にURL短縮が行えます。
利用は無料ですが、別途、独自ドメインでの短縮URLを生成できる有料サービスも展開されています。
Tiny.cc
こちらもWeb上で簡単に短縮URLを生成できるほか、「tiny.cc」ドメインに続く文字列部分については任意の文字列を指定したうえでの生成にも対応しています。別途、独自ドメインに対応した有料サービスもあります。
X.gd
登録やログイン不要ですぐに利用できる、国産のURL短縮サービスです。
比較的項目が多めのアクセス解析機能も利用でき、分かりやすい日本語での公式説明があるため理解もしやすいでしょう。
Ow.ly
こちらは有料のSNS管理ツール「Hootsuite」上で利用できるURL短縮機能です。
SNSマーケティング活動の全体的な効率化と合わせて、URL短縮も実現したいという場合におすすめです。
Cuttly
URL短縮のほか、アクセス解析機能も利用できるサービスです。
合わせてQRコード生成もできるため、手間いらずのアクセス方法で訴求力を強めたい場合にもおすすめです。
Short.io
大手国内企業での利用実績もある、多機能型の有料ツールです。
URL短縮のほか、クリック状況のリアルタイム追跡、キャンペーン追跡、ドメイン部分のカスタマイズなどマーケティングで役立つ機能が満載です。
Chrome拡張機能としても提供されているため、導入が簡単なことも特長です。
まとめ:Googleの短縮URLを運用している方は早めに準備!
本記事では「Google URL Shortener(goo.gl)」の2025年8月提供終了に関連して、短縮URLのニーズや仕組み、代表的な他の人気サービスなどをご紹介しました。
現在「goo.gl」を社内や対外的に活用している方や、そうでなくともこれから短縮URLでの運用を検討しているご担当者様は、今回ご紹介した内容をぜひマーケティング活動に活かしてください。
▼Webマーケティングにおける効果の停滞・対応リソース不足といった課題をお持ちのご担当者様は、お気軽にProFutureのマーケティング支援サービスへご相談ください。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/

