ロイヤリティとは、顧客が特定の企業やブランド、サービスなどに対して持つ継続的な愛着や信頼を指します。商品やサービスの品質だけでなく、ブランドの世界観や顧客体験全体が評価されることで、消費者が「次もこのブランドを選びたい」と感じる状態です。
しかし、多くの企業が「顧客満足度を上げればロイヤリティも向上する」と考えていますが、それだけでは不十分です。
現代の消費者は「いろいろ試してみたい」という欲求を持ち、たとえ商品に満足していても、より魅力的な選択肢を見つければ簡単に別のブランドへ移ることがあります。そのため、単なる満足度向上ではなく、顧客がブランドと深く結びつく心理的ロイヤリティや行動的ロイヤリティを高めるマーケティング戦略が必要になります。
本記事では、ロイヤリティの基本概念を整理しながら、どのようにして顧客のロイヤリティを向上させるか、その具体的な戦略と成功事例を詳しく解説します。
目次
ビジネスとマーケティングに関係する3つのロイヤリティ

ロイヤリティという言葉は、さまざまな形で使われますが、ビジネスにおいては以下3つのロイヤリティが重要となります。
・ブランドロイヤリティ
・顧客ロイヤリティ
・従業員ロイヤリティ
まずは、各ロイヤリティの特徴を見ていきましょう。
ブランドロイヤリティ
ブランドロイヤリティとは、特定のブランドや製品に対する顧客の継続的な支持や愛着を指します。
たとえば、スマートフォンを買い替える際、スペックや価格を比較する前に「iPhoneだから選ぶ」と決めるような行動がそれに当たります。競合他社の製品と比較することなく、同じブランドの商品を自然に選び続けるのが特徴です。
このロイヤリティは、製品の品質やデザイン、ブランドの世界観、広告戦略などによって形成されます。ブランドロイヤリティが高い顧客は、多少価格が高くてもそのブランドを選び、他のブランドへ乗り換える可能性が低くなります。
顧客ロイヤリティ
顧客ロイヤリティ(顧客ロイヤルティ)は、ブランド単体ではなく、企業そのものに対する信頼や愛着を指します。
特定のブランド・製品だけでなく、企業が提供するさまざまな製品やサービスを継続的に利用する点が特徴です。
たとえば、AppleのiPhoneを愛用するだけでなく、MacやiPad、Apple Watchなども積極的に選ぶ人は、Appleという企業自体に対して強いロイヤリティを持っているといえます。
また、商品の性能だけでなく、カスタマーサポートの対応や企業の理念、社会貢献活動に共感して支持し続けるのも顧客ロイヤリティの表れです。
ブランド単体の魅力だけでなく、企業全体への信頼を築くことで、新商品やサービスを展開した際も顧客の支持を得やすくなります。
関連記事:戦国時代を通じて、現代でも有名となった伊達政宗・真田幸村たちのブランディング手法【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第6回】
従業員ロイヤリティ
従業員ロイヤリティとは、社員が自社に対して持つ信頼の愛着のことを指します。
ロイヤリティの高い従業員は積極的に会社に貢献し、業務に対して主体的に取り組む傾向があります。特に、カスタマーサービスやマーケティングの分野では、従業員のロイヤリティが高いほど、顧客体験の質も向上し、結果として顧客のロイヤリティ向上にもつながります。
関連記事:信長・秀吉・家康たち戦国武将のインターナルマーケティング【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第4回】
なお本記事では、ブランドロイヤリティと顧客ロイヤリティについてお伝えします。
顧客のロイヤリティを高め、「企業やブランドのファン」になってもらうことの大切さ

ここで余談ですが、「Loyalty(ロイヤリティ)」は、「忠誠心」や「愛着」といった意味を持ちます。
一方で、混同しやすい単語に「Royalty(カナでは一般的に「ロイヤルティ」と表記されることが多い)」があります。こちらは「気品」「気高さ」といった意味のほか、特許や著作権に関連する使用料(ロイヤリティ)の意味でも使われます。たとえば、「ロイヤルティ溢れるアクセサリー」といった表現は、「Royalty」に該当します。
関連記事:著作権とは?制作担当者が知っておくべき保護の期限・期間や侵害しないための基礎知識&ミッキー事例も紹介
話は戻り、顧客のロイヤリティ(Loyalty)を高めれば、以下のメリットを得られます。
・リピート率の向上、解約率の低下
・顧客単価、LTV(ライフタイムバリュー)の向上
・ファン化によるPR効果
・ブランドイメージの向上、強化
顧客ロイヤリティを数値化する手法の一つに、「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」があります。これは、「この商品やサービスを友人や同僚に勧めたいと思うか?」という質問に対する顧客の評価を0〜10のスコアで測定するものです。
NPSが高い企業は、ロイヤリティの高い顧客を多く抱えていることを意味し、長期的に安定した成長が期待できます。さらに、NPSの高い推奨者(スコア9〜10)は、積極的に口コミを広める可能性があり、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)の発生にもつながります。
こうしたユーザーが投稿したコンテンツを公式サイトやSNSで活用することで、さらなるロイヤリティ向上を実現できるでしょう。
▼以下の記事でも、NPSやUGCについて深掘りして解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
「NPS」とは? 顧客ロイヤルティを測る経営指標について
UGCとは?今注目されている理由と具体的な手法を徹底解説
顧客のロイヤリティが重要視される背景

それでは、なぜ顧客のロイヤリティが重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、消費者の購買行動の変化、市場の競争激化、デジタルマーケティングの進化といったさまざまな要因があります。
ここからは、顧客のロイヤリティが重要な理由を見ていきましょう。
Web広告施策だけでの新規顧客獲得が難しい時代に
かつては、広告出稿によって新規顧客を獲得し、継続的な売上を確保することが可能でした。
しかし、近年ではWeb広告の効果が低下し、新規顧客獲得コスト(CAC)が上昇しています。その主な理由は2つです。
1つ目は、単純に広告を出稿する企業が増加したことです。
電通の「2023年 日本の広告費」によれば、Web広告費はすでにマスコミ四媒体広告費を上回っており、総広告費の45.5%を占めます。これはWeb広告に取り組む企業の増加を意味し、競合が多くなることで、新規顧客獲得コストが増加するのです。
2つ目がターゲティング広告の精度低下です。
GoogleやAppleによるプライバシー保護の強化(サードパーティークッキーの廃止)により、ターゲティング広告の精度が下がり、広告のパフォーマンスが悪化しています。以前のように効率的にターゲットユーザーにリーチすることが困難です。
消費者側の得られる情報の幅や地域的な制約がなくなったからこそ「ロイヤリティ」が競争率に直結
インターネットやSNSの発展により、消費者はこれまで以上に自由に情報を収集し、世界中のあらゆる商品やサービスを比較・検討できるようになりました。
地域的な制約がなくなったことで、オンライン上の口コミやレビュー、SNSでの評判が購買行動に与える影響はますます大きくなっています。
キャプテラの調査結果が公表されているページ「SNSで商品検索するオンライン消費者:過大な広告を嫌い、リアルなレビューを求める」によると、日本のネットショッピング利用者の7割がGoogleやYahoo!などの検索エンジンを使って商品やサービスを調べると回答しています。一方で、InstagramやTikTokなどのSNSを活用すると答えた人も28%に上ることが明らかになりました。
この結果からもわかるように、消費者は公式サイトの情報だけでなく、実際のユーザーの声やSNSでの評判を参考にして購入を決めているのです。
かつては、地域の店舗や知名度のある企業が自然と選ばれることが多かったものの、現在では「どこで買うか」よりも「誰が推奨しているか」「他のユーザーがどう評価しているか」が意思決定に大きく影響を及ぼします。
こうした環境では、単に「良い商品・サービスを提供する」だけでは差別化が難しくなり、競合と比較されることで簡単に顧客が離れてしまうリスクが高まります。
たとえば、競合が価格を下げれば、コスト面での優位性がなくなり、企業は利益率の低下を招く価格競争に巻き込まれてしまうでしょう。
このような状況の中で、顧客ロイヤリティを高めることが、企業にとって重要な戦略となります。
ロイヤリティの高い顧客は、単なる価格や機能の比較ではなく、「このブランドだから」「この企業の商品なら信頼できる」という理由で選択するため、価格競争に巻き込まれるリスクが低くなります。
消費者があらゆる選択肢を持てる時代だからこそ、企業は顧客との長期的な関係を築き、「ファン」としてのロイヤリティを獲得することが、競争力を維持するための決定的な要素となっているのです。
関連記事:ファンマーケティングとは?メリット・デメリットやポイント、成功事例を解説
「商品を気に入った、買って良かった」だけでは次も選んでもらえるとは限らない
「顧客満足度が高ければリピート購入につながる」という単純な時代は終わりました。
かつては、品質や価格に満足すれば自然と同じブランドを選ぶ傾向がありましたが、現代の消費者は「気に入った商品を買う」だけでなく、「さまざまな選択肢を試してみたい」という欲求を持っています。
Googleは「パルス型消費行動」という消費者行動を提唱しました。
これは、商品を購入する際の意思決定が一貫したものではなく、その時々の情報や状況に応じて変動することを意味します。たとえば、以前は「このブランドの化粧品が気に入ったから、次も同じものを買おう」と考えていた消費者も、SNSやレビューサイトで新しい商品を見つけると「試してみたい」という気持ちが生まれ、簡単に他のブランドへと流れてしまいます。
消費者が商品を「気に入った」だけでは、次回も選んでもらえる保証にはならないのです。むしろ、ブランドや企業との「つながり」を感じてもらうことが重要になります。
顧客がブランドを単なる選択肢の一つとして捉えるのではなく、「このブランドだから購入したい」「この企業の価値観に共感する」と思ってもらうことが、長期的なロイヤリティを確立する鍵となります。
関連記事:消費行動は「カスタマージャーニー型」から「パルス型消費」へ変化しているのか?
マーケティングにおいて「ロイヤリティ」と「エンゲージメント」はどう違う?

ロイヤリティとエンゲージメントは、どちらもマーケティング戦略において顧客との関係を深める上で重要な概念ですが、それぞれの意味や役割は異なります。これらを正しく理解し、適切に活用することが、効果的なマーケティング施策の推進には欠かせません。
エンゲージメントとは、顧客がブランドとの関係において示す積極的な関与や参加を指します。単に商品を購入するだけでなく、ブランドのSNSをフォローしたり、口コミを投稿したり、コンテンツに反応したりする行動が含まれます。
特にデジタルマーケティングにおいては、「いいね」や「シェア」、「コメント」などのSNS上のアクションがエンゲージメントの指標として用いられ、ブランドと顧客の相互作用を強化する要素として重視されます。
関連記事:エンゲージメントとは?マーケティングにおける意味合いを徹底解説
一方、ロイヤリティは、顧客が特定のブランドや企業に対して持つ継続的な愛着や信頼を意味します。エンゲージメントの積み重ねではなく、顧客がブランドを「自分にとって特別な存在」と認識し、長期的な関係を築くことによって生まれるものです。
ロイヤリティとエンゲージメントは常に密接に関連しており、エンゲージメントが高い顧客は、ロイヤリティの高い顧客へと転換する可能性が高いといえます。
「心理的ロイヤリティ」と「行動的ロイヤリティ」の違い

ロイヤリティには、「心理的ロイヤリティ(Psychological Loyalty)」と「行動的ロイヤリティ(Behavioral Loyalty)」という2つの種類があり、それぞれが企業のマーケティング戦略に与える影響は異なります。
以下では、2種類のロイヤリティについて見ていきましょう。
心理的ロイヤリティ
心理的ロイヤリティとは、顧客がブランドに対して抱く感情的なつながりや愛着を指します。
「便利だから」「コスパが良いから」といった合理的な理由で選ぶのではなく、ブランドの理念や価値観に共感し、「このブランドを応援したい」「この企業の製品を使い続けたい」と感じることが特徴です。
たとえば、Appleの製品を愛用し続ける顧客の中には、単にデザインや機能が優れているからではなく、Appleの哲学やイノベーションへの姿勢に共感している人が多くいるでしょう。
BtoBの例を挙げれば、HubSpot Incの「インバウンドマーケティング」の思想に共感し、単なるツールではなく、企業の成長を支援するパートナーとして同社を信頼する企業も少なくありません。
心理的ロイヤリティが高い顧客は、多少価格が高かったり、多少の不便があったりしても、競合他社には簡単に乗り換えません。それは、ブランドとの関係が単なる取引を超えた「信頼」と「共感」にもとづいているためです。そのため、こうした顧客を増やすことは、企業にとって長期的なブランド価値の向上につながります。
行動的ロイヤリティ
行動的ロイヤリティとは、顧客が実際にブランドの商品やサービスを繰り返し購入・利用する行動のことです。
心理的な愛着や共感というよりも、価格の安さ、利便性、ポイントプログラムなどのインセンティブによって形成されることが特徴です。
スーパーマーケットやECサイトが導入するポイントプログラムは、行動的ロイヤリティを高める典型的な施策です。
顧客が特定のスーパーで買い物を続ける理由は、「このブランドが好きだから」ではなく、「ポイントが貯まるから」「家の近くにあって便利だから」といった合理的な要因が大きいでしょう。
また、定期購入サービスやサブスクリプションモデルも、利便性やコストメリットを提供することで、顧客の継続利用を促しています。
関連記事:サブスクリプションとは?ビジネスモデルの特徴や代表的なサービスを紹介
行動的ロイヤリティが高い顧客は、必ずしもブランドに対して強い愛着を持っているとは限りません。「他に選択肢がないから」「乗り換えの手続きが面倒だから」といった消極的な理由で利用を継続する場合もあります。
行動的ロイヤリティを高めれば、短期的な売上の安定につながります。しかし、価格や利便性だけに依存すると、競合がより魅力的な条件を提示した際に顧客が簡単に離れてしまうリスクが生じるのです。
そのため、行動的ロイヤリティを維持しつつ、ブランドの価値やストーリーを伝え、心理的ロイヤリティへと発展させることが、長期的な成長の鍵となります。
ロイヤリティマーケティングの手法と進め方

ロイヤリティマーケティングを成功させるためには、現状の顧客ロイヤリティを測定・分析し、適切なKPIを設定した上で施策を実行し、継続的に改善していくことが重要です。
以下では、ロイヤリティマーケティングの進め方を解説します。
現状のロイヤリティの把握・数値化
まず自社の顧客がどれほどのロイヤリティを持っているのかを正確に把握します。
どの顧客層がブランドに対して強い愛着を持ち、どの層が離脱のリスクを抱えているのかをデータで分析すれば、より効果的な施策を立案できるようになります。
以下の指標を用いて、現状の顧客ロイヤリティを把握しましょう。
・NPS
・リピート購入率
・LTV
・解約率
たとえば、NPSが高い「推奨者」にはアンバサダープログラムを展開し、口コミをさらに促進します。逆に、NPSが低い「批判者」に対しては、満足度の低い要因を分析し、カスタマーサポートの強化やサービス改善を図るといった施策が考えられます。
このように、ロイヤリティの現状を把握すれば、データにもとづいて最適なマーケティング戦略を立案できます。
KPIの設定
ロイヤリティマーケティングは、一度の施策で劇的な成果が出るものではありません。
顧客との関係を深め、ロイヤリティを高めるには、継続的な分析と改善のサイクルを回していくことが重要です。そのためにも、明確なKPIを設定し、進捗を数値で把握できるようにしましょう。
ロイヤリティ向上を目的としたマーケティング施策を実施する場合、以下のようなKPIを設定することで、成果を測定しやすくなります。
・NPSを10ポイント向上させる
→ 顧客の推奨意向が高まり、ブランドのファンが増えているかを測定
・リピート購入率を20%から25%に引き上げる
→ 施策が既存顧客の継続購入に貢献しているかを確認
・LTVを30%向上させる
→ 顧客単価の向上やリピート頻度の増加を指標として追う
・解約率を5%低減させる
→ サブスクリプション型ビジネスにおけるロイヤリティの維持・向上を評価
・ロイヤリティプログラム会員数を1年間で50%増加させる
→ 顧客がブランドとの関係を深める仕組みが機能しているかを測定
また、KPIを設定する際は、定量的な指標と定性的な指標をバランスよく組み合わせることが重要です。数値だけでなく、顧客の声やブランドに対する感情的なつながり(心理的ロイヤリティ)なども考慮しながら、より精度の高いロイヤリティマーケティングを実現していきましょう。
関連記事:KPIツリーの具体的なつくり方をKGIの設定含めて解説!
目標とKPIに応じた特典プログラムを検討
ロイヤリティ(特に行動的ロイヤリティ)を高めるには、顧客に価値ある特典を提供することが重要です。
特典には、大きく分けて「ハードベネフィット」と「ソフトベネフィット」の2種類があります。
【ハードベネフィット(直接的な特典)】
・割引、キャッシュバック
・ポイント制度
・無料アップグレード
・サンプル商品
【ソフトベネフィット(感情的な価値を提供)】
・限定アクセス
・会員限定イベント
・称号の付与
・感謝メッセージ
特典プログラムを設計する際には、ハードベネフィットとソフトベネフィットのバランスを取ることが重要です。
ハードベネフィットだけでは価格競争に巻き込まれやすく、競合がより大きな特典を提供すれば簡単に顧客が流れてしまうリスクがあります。一方、ソフトベネフィットだけでは、短期的な行動を促す力が弱く、継続的な利用を生み出しにくいという課題があります。
そのため、KPIに応じて特典の種類やバランスを調整し、顧客が長期的にブランドと関わり続けたくなる仕組みを作る必要があります。
ロイヤリティにつながるマーケティング施策の検討
顧客ロイヤリティを高めるためには、顧客との継続的な関係を築く仕組みが重要です。具体的なマーケティング施策と期待できる効果は以下の通りです。
【ファンコミュニティの運営】
ブランドのファン同士が交流できる場を提供し、ロイヤリティを深める施策
・ユーザー同士のつながりが強まり、ブランドへの帰属意識が向上
・企業が顧客の声を直接聞けるため、商品開発や改善に活かしやすい
・コミュニティ内で自然発生的な口コミや情報共有が生まれる
【アンバサダープログラム】
ロイヤリティの高い顧客を公式アンバサダーとして認定し、ブランドの魅力を広めてもらう施策。
・影響力のあるファンがブランドの魅力を発信し、新規顧客の獲得につながる
・広告費を抑えながら、より自然で信頼性の高い口コミを生み出せる
・アンバサダー自身のエンゲージメントも向上し、LTVの増加が期待できる
関連記事:アンバサダー(Ambassador)とは?アンバサダーマーケティングの意味や事例
【リファラル(紹介プログラム)】
既存顧客に友人や家族を紹介してもらい、新規顧客獲得を促進する施策。
・既存顧客が積極的に紹介することで、質の高い新規顧客を獲得できる
・報酬(割引やポイント)を提供することで、既存顧客の満足度やリピート率も向上
【UGCの活用】
ユーザーが自発的に作成した写真・動画・レビューなどを活用し、ブランドの信頼性や魅力を伝える施策。
・実際の利用者の声を発信することで、広告よりも信頼性の高い情報を提供できる
・UGCを公式サイトやSNSに掲載することで、新たな顧客の興味を引きやすい
・ユーザー自身がブランドに関与することで、ロイヤリティが向上
【オウンドメディア・ファンサイトの運用】
企業が独自に運営するWebサイトやブログを通じて、ブランドの価値やストーリーを発信する施策。
・企業視点ではなく、顧客目線での情報提供ができるため、エンゲージメントが向上
・SEO対策としても機能し、長期的な集客効果が期待できる
・ブランドの世界観やストーリーを伝え、ファン層の定着を促進
これらの施策に共通するのは、企業と顧客が一緒にブランドを育てる関係を築くことです。
広告やプロモーションのような一方通行の発信ではなく、顧客自身がブランドの一部として関与できる環境を作ることで、「このブランドだからこそ選びたい」というロイヤリティの向上につながります。
自社の顧客層やブランド特性に合った施策を選び、ロイヤリティの高いファンを創出しましょう。
関連記事:オウンドメディアとは?意味や運用する目的、ホームページとの違い、具体的な成功事例を解説
施策の実行と効果検証、改善
ロイヤリティ向上のための施策を実行した後は、その効果を定期的に分析し、PDCAサイクルを回しながら改善を重ねていくことが重要です。
施策の評価には、定量的なデータと定性的データ(顧客の声)の両方を活用しましょう。NPSやリピート購入率、LTVなどの数値を追いながら、顧客のレビューやフィードバックを分析し、「なぜロイヤリティが向上したのか」「なぜ離脱したのか」といった背景を理解することが大切です。
また、施策の成果が思うように上がらない場合は、KPIの見直しや、ターゲットに合わせた特典の調整、コミュニケーション方法の最適化など、具体的な改善策を講じる必要があります。
ロイヤリティマーケティングは、一度実施すれば完了するものではなく、市場環境や消費者行動の変化に適応しながら進化させていくものです。データと顧客の声をもとに継続的に改善を重ね、長期的にブランドとの関係を深める施策へと発展させていきましょう。
関連記事:PDCAとは!時代遅れといわれる理由やOODAとの違いについて解説!
▼自社の認知度やブランド力アップ、商品やサービスのプロモーションに課題をお持ちであれば、ProFutureのマーケティング支援サービスへご相談ください。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/
▼ホームページ / オウンドメディアの集客増、リピーター獲得に課題をお持ちであれば、ProFutureのWebマーケティング支援「HR SEO」へご相談ください。企画・制作から運用まで一気通貫でお任せいただけます。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/3040
顧客ロイヤルティ向上に成功した事例
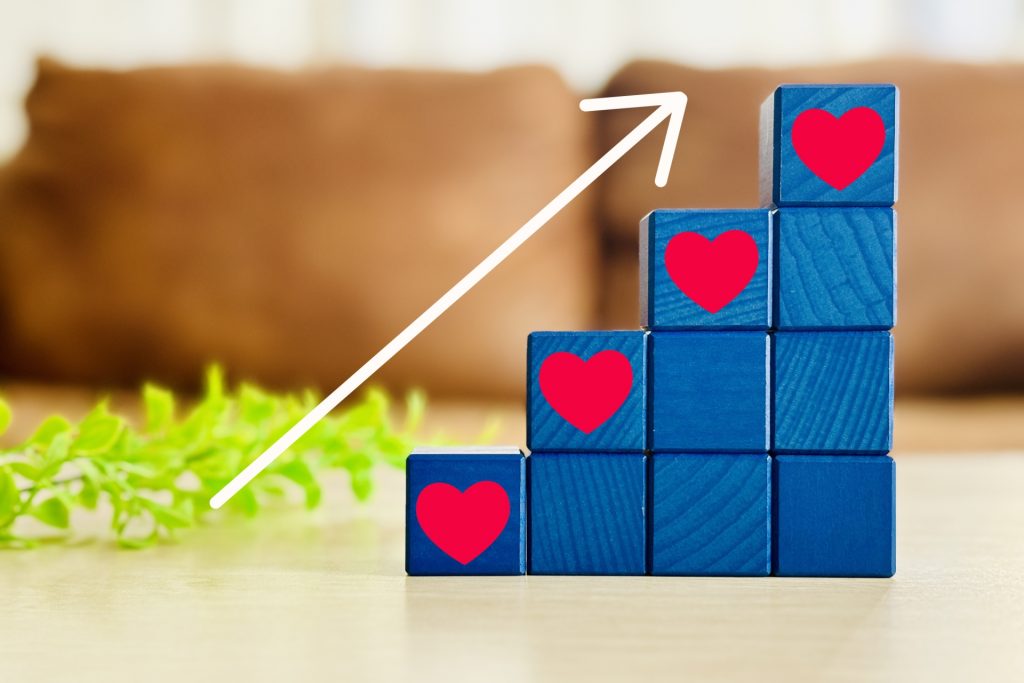
ここでは、異なる業界で顧客ロイヤリティ向上に成功した企業の事例を紹介し、それぞれの戦略と成果について詳しく解説します。
事例①:保険業A社におけるNPS活用と顧客体験の改善
A社は、競争の激しい保険業界において、カスタマーエクスペリエンスの向上を通じた顧客ロイヤリティ強化に取り組みました。
まず、顧客ロイヤリティを測定・改善する指標としてNPSをKPIに設定。従来の市場調査では把握しきれなかった個別の顧客課題を明確化し、一人ひとりの満足度を詳細に分析し、より的確な改善策を立案することが狙いです。
次に、SMS・Eメール・コールセンターを活用したリアルタイムの顧客フィードバック収集・分析システムを構築。顧客の声を即時に把握できる仕組みを整え、問題点の優先度を自動的に設定することで、迅速な対応が可能になりました。さらに、効果が高い施策は他の拠点にも素早く展開され、組織全体での改善が推進されるようになりました。
この取り組みの結果、ある国ではNPSが20%向上するなど、顧客ロイヤリティの大幅な向上と継続率の改善を実現しました。
事例②:食品・飲料業B社のファンコミュニティ活用戦略
B社は、自社の定期購入サービスの新規会員獲得を強化するため、UGC活用ツールを導入しました。
導入当初は、定期購入のメリットや楽しみ方に焦点を当てたUGCを掲載していましたが、データをもとに検証を進める中で、ライフスタイルや「商品があることで生まれる日常の幸福感」を伝える投稿が、より高い効果を発揮することが判明。
これを受けて、より共感を呼ぶUGCを厳選して掲載するよう改善した結果、ファンの熱量が高まり、売上向上につながる成果を上げました。
この取り組みは、ファンのリアルな声を活用し、ブランドの世界観を自然に伝えることで、新規顧客の獲得と既存顧客のエンゲージメント強化を同時に実現した好例といえます。
事例③:エンタメ業C社のサブスクリプションとD2C戦略の融合
C社は、公式通販サイトのリニューアルにあたり、ファンビジネス向けのトータルCRMソリューションとポイント管理ソリューションを導入しました。
まず、会員専用のマイページを作成し、ファンに対する特別な体験を提供。有料会員限定のコンテンツ配信や会員の興味・購買履歴に応じたメルマガ配信、ターゲットに最適化したキャンペーン施策を実施できるようになりました。
さらに、ポイント管理システムを活用し、商品購入時のポイント付与や魅力的な自社オリジナルグッズとの交換を可能にすることで、継続的な購買意欲を高め、エンゲージメントの強化を実現しました。
この取り組みにより、C社はファンのロイヤリティを深めるだけでなく、D2Cモデルを強化し、サブスクリプションとECの相乗効果の最大化に成功。
データドリブンなアプローチを取り入れることで、ロイヤルカスタマーの育成がスピーディーに進み、より効果的で実践的なデジタルマーケティング施策の立案・実施が可能となりました。
関連記事:D2Cとは?ECにおけるビジネス展開が成功した例をわかりやすく解説
まとめ:自社ならではの施策で顧客の愛着・信頼を獲得! ロイヤリティマーケティングが現代ビジネスのカギ
本記事では、ロイヤリティマーケティングの重要性と、それを実現するための具体的な戦略について解説してきました。
ロイヤリティの向上は、単に顧客を引き止めるための手法ではなく、ブランド価値を高め、持続的な成長を実現するための鍵となります。
デジタル化が進む現代では、消費者が自由に情報を入手し、比較・検討できる環境が整っています。価格や機能だけでは競争に勝ち続けることは難しく、顧客に選ばれ続けるためには、心理的ロイヤリティと行動的ロイヤリティの両面を意識した施策が必要となるのです。
▼エグゼクティブや専門家、マーケティング業界関係者の方々との情報共有、人脈づくりやネットワーク強化にはProFutureのイベント(サミット、フォーラム、セミナー)をご活用ください!
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/event/14

